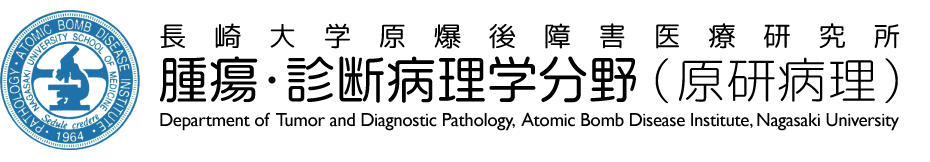教授就任12年にあたり
2010年3月、この原研病理の主任を拝命して、12年が経ちました。教室ホームページの「教授あいさつ」を最後に更新したのは7年前の平成27年3月です。教授としての折り返し地点は既に過ぎ、この機会にこれまでの12年を振り返り、残りの任期に当たりたいと考えます。
研究について:論文や学会発表の業績はこのHP中に掲載している通りです。この12年間で教室が主となり発表した論文は38編で、うち学位論文は9編含まれます。教室の研究テーマの柱は甲状腺を中心とする腫瘍病理学、原爆被爆者腫瘍・放射線関連発がん、新規分子病理診断指標研究で、この12年間変わっていません。現在進行中の研究課題は、1)甲状腺腫瘍内の組織構築の不均一性を分子病理学的に説明すること、2)「長崎被爆者腫瘍組織バンク」試料を用いた網羅的遺伝子解析による放射線誘発変異の特徴を発見できるか、またラット放射線誘発甲状腺癌モデルによる被ばくの分子指標を同定できるか、3)DNA損傷応答分子である53BP1は悪性腫瘍の普遍的な分子病理診断マーカーとなるか、というものです。これらの課題に関して学生や教員が学会発表し、病理学会学生発表賞、臨床内分泌病理学会研究賞、欧州病理学会の口演賞とポスター賞、国際臨床細胞学会のベストポスター賞、甲状腺学会研究賞と多数の表彰をいただいたのは今後の励みになりました。しかし、それぞれ難しいテーマであり、残念ながらまだまだゴールには程遠いと言わざるを得ません。今後も教室員と一緒に取り組み、甲状腺結節の病理診断への新提言、近距離被爆者腫瘍の遺伝子変異の網羅的解析、53BP1の病理診断への臨床応用の3つに挑戦していきたいと思います。
病理診断について:先代からの県内の病院の病理診断に加え、令和2年度より長崎大学病院地域病理診断支援センターが創設され、我々が担当することになりました。長崎県病院企業団からの委託で、現在令和4年度は助教、助手、医員3つのポストを得て、五島中央病院、上五島病院、対馬病院の病理診断と大学病院の病理診断の一部を担当しています。さらに令和元年からは甲状腺専門病院の病理診断を担当しています。多数の甲状腺・副甲状腺病変の病理を経験する機会に恵まれた幸運に感謝します。甲状腺腫瘍病理の共同研究もさせていただいていて、教室にとっては財産です。教室の病理専門医の養成に必要な十分な病理診断体制(剖検数を含め)は数的にも質的にも整っています。実際、12年間で教室から3名の病理専門医が生まれ、現在2名が長崎大学病理専門医プログラムでの修練中です。令和2年11月現在、我が国の病理専門医数は2620名、長崎県は27名です。これは人口10万人あたり2.0名に相当し、全国平均2.1名と同等ですが、10名(37%)が65歳以上と高齢化が顕著です。我が国の病理診断件数は2005年の2,143,452件から2018年は4,614,585と約2.2倍に増加、術中迅速件数は同57,684件から228,754件(約4.0倍)、がんの治療を決定する免疫染色件数は同151,248件から426,276件(3.8倍)と急増しています(厚生労働省 大臣官房統計情報部調査)。これらの数字を見ても病理専門医の現状は不足していることが明らかです。患者さんへの正確な病理診断提供のため、初期研修から県内の病院と大学との連携で専門医を育成する体制が必要と考えます。研修指定病院の長崎医療センターや嬉野医療センター、諫早総合病院の病理診断科には、原研病理同門の病理医が常勤していて、その連携で長崎県内の病理医を増やして参ります。
まとめ:この12年間で大学の運営体制、財政状況はドラスティックに変化しました。研究費獲得には常に競争力が問われるし、研究組織や教育プログラムはbuilt and scrapで新規性や革新性を持った改編が求められます。我々の所属する原爆後障害医療研究所は9年前(2013年)に大学附置研究所に改組され、6年前にはネットワーク型共同利用・共同研究拠点に認定されました。大学院専攻としては金沢・千葉大学との3大学共同の博士課程と福島医大との2大学共同の修士課程が新設され、原研の教室には多数の学生が所属して学んでいます。新型コロナのパンデミックやロシアのウクライナ侵攻といった社会不安は突発的に発生し、教育や研究活動に大きな変化を強いてきます。我々の課程の学生には旧ソ連邦圏の留学生が多く、将来に不安を抱えながら学業の継続を望む学生が少なくありません。変化のスピードの著しい大学の研究・教育環境や社会情勢からの影響に対応しながら、教室主任としての任にあたるには、教室員というマンパワーの活用と教員の目的意識の新陳代謝を促していくことが必要と考えます。教授就任時には二人病理医の困難な時期もありましたが、現在まで多くの同門の先生、共同研究者、教室員、大学院生に支えられて、これまで業務をこなしてきました。私の教室主任としての職務は、若い人材が集まり、ともに学び成長し、活躍・貢献できる場を与えることです。それには教室員全員に目的を共有してもらう事と若い人材を育てようとする想い・愛情が必要です。残された任期で、教室員と共により良い教室を作っていきたいと思います。
腫瘍・診断病理学研究分野(原研病理)
教授 中島 正洋
開講50周年に思うこと
長崎大学における病理学講義は、1857年にポンペが開講した「原病学」に始まり、これがすなわち日本の病理学の原点にもなります。1859年1月1日にポンペが定めた講義表には、病理総論が週3コマ月、水、金曜日の午前中に病理総論が組まれ、解剖学、化学、生理学とともに主科目のひとつでした(小路武彦、相川忠臣;「ポンペの解剖学教育」解剖学雑誌2008)。「病気は細胞の質的・量的変化によって生じる」としたウィルヒョウの細胞病理学は1855年に出版されました。病理学講義録である「朋百原病総論」は、それ以前の臓器病理学や体液病理学時代の学説に拠っていたことが示されていますが、ボードウィンからマンスフェルトに受け継がれ、我が国の病理学教育に大きく寄与しました。「病理学」の過程名は1868年(明治元年)の長崎府医学校の学科序目に初めて認められ、病理学教室が第1、第2と二つに分かれたのは1926年(大正15年)でした。
原研病理の歴史は、1964年(昭和39年)8月16日、西森一正教授就任をもって始まりました。当時本邦血管病理の第一人者であった松岡 茂第2病理学教授に師事されていて、第2病理助教授からの異動でした。ご自身も腎・血管病理の分野で活躍され、「心因性ストレスと血管病変」がひとつのテーマでありました。さらに原爆被爆者の剖検・生検資料の整理収集を体系づけられ、病理疫学的な多数の貴重な業績を残されています。1987年(昭和62年)3月には関根一郎助教授が第2代教授に就任、被爆者後障害の病理疫学研究は継承されていきます。関根教授は、医学部卒業後、熱帯医学研究所の病理学部門助手となられ、コレラの系統的病理学研究で学位取得後、昭和50年10月に熱研病理から西森先生の原研病理へ移籍されました。消化管病理が専門で、放射線治療誘発大腸がんの病理像・防護薬研究とストレス潰瘍研究の分野でご活躍されました。特に、実験潰瘍学会で論争されていましたストレス潰瘍における交感神経善玉説を、実験動物を用いて見事に証明されたこと、さらに自律神経支配が放射線障害に個体差として影響することを見出された業績は、その後の各領域の研究に大きなインパクトを与えました。西森教授はご自身で「近距離被爆の数少ない生き残りとして私にとって原研は宿命的職場であったかも知れない」と「原研25周年記念誌」の中で述懐されています。西森・関根両教授は放射線病理の研究者であると同時に被爆者でもあり、広島と長崎の経験を人類の医学的知識に体系化に尽力され、教室を継承、発展させてこられました。
原研施設は2013年(平成25年)創設51年目で研究所となり、医学部から独立しました。研究所ですので研究がミッションの中心となるのですが、学部・全学教育は今まで通りに担当しています。医学部と同格として学内で評価される部局となり、新しい競争環境に身を置くことになりました。原研病理は原爆後障害医療研究施設の病態生理学部門として創設され、現在まで病理学教室として継続しています。日本病理学の偉人、吉田富三は、1943(昭和18)年、長崎医科大学第2病理の教授時代に「長崎系腹水肉腫/吉田肉腫」を発見しました。当時、「吉田肉腫」は化学療法の有効性評価などの研究に広く用いられ、多数の研究業績につながりました。その中で、腫瘍細胞の移植が1個の細胞で十分であることが明らかにされています。この結果はまさに、現在のトピックスである「がん幹細胞」の存在を予言するものであり、特筆すべき業績です。吉田富三は「顕微鏡を考える道具とした最初の思想家」と称されます。昭和14年の卒業アルバムには「人間の歩みには本来方向だけがあって到着地はないものだと思う。従ってその方向の認識如何が実に各々の人間を決定する。一人の人間がどんな方向をとって居るかは些細な事柄にも実に明瞭に表現されるようである」と記し、掲げる目標とその継続性の重要性を挙げています。
私は診断病理学と放射線の人体影響研究を教室のミッションとして掲げました。放射線被曝と甲状腺発がんはあまりにも有名ですが、発がんに至る過程の慢性甲状腺障害の病態や年齢影響の分子機構は、実はまだほとんど解明されていないと思っています。放射線発がんのみならず、一般的発がん研究につながると確信し、教室全体で取り組んで明らかにしたい研究課題です。被爆者の教授が既に大学から退職され、原研は改組しても、原研病理として見据えるゴールは西森・関根病理と基本的には同じです。私が主任となり、あっという間に5年が経過しました。平和時においてもチェルノブイリや福島のような原子力事故は起こりうるし、地球上には未だに多くの核兵器が存在することを考慮すれば、広島・長崎の経験のもつ意義の重さは自明です。教室創設当時の故西森先生に思いを馳せ、関根先生からの放射線病理の伝統を継承し、温故創新の発想で長崎大学と病理学の発展に貢献していこうと決意を新たにしているところです。
開講50周年記念誌(2015年3月発行)より
腫瘍・診断病理学研究分野(原研病理)
教授 中島 正洋
近況報告
本年度、原研は創設50周年を迎えました。その記念式典が、原研が事業協力をしています長崎ヒバクシャ医療国際協力会(NASHIM)の設立20周年との共催で、この2月にベストウエスタンプレミアホテル長崎で開催されました。永井隆平和記念・長崎賞授賞式や合同シンポジウム「長崎とヒバクシャ医療−被ばく医療学の新たな挑戦:国際貢献・そして福島」、被ばく者医療セミナーが主な内容でした。平成25年度、原研は学内措置により、大学院医歯薬学総合研究科附設から研究所に昇格されることになりました。今後、文部科学省の「共同利用・共同研究拠点」に応募し、大学の枠を越えて全国の研究者が共同利用できる拠点になることを目指します。現在、共同利用・共同研究拠点として、約80の大学附置研究所・施設が認定されていて、本学の熱帯医学研究所や広島大学の原爆放射線医科学研究所がそれに当たります。うまく認定されることになると、設備の整備や共同利用に係る経費について、国から重点的に予算配分が行われます。原研としての51年目は、研究所としての新たなスタートの年となります。
人事異動についてご紹介します。社会人大学院生から助教に松田さんを採用しました。大学病院の婦人科で年間4000例を一人で担当していた臨床細胞検査士で、婦人科腫瘍が得意分野です。子宮頚部腫瘍の分子病理で、この昨年度に学位を取得しました。5月から放射線発がんの個体差について研究をしてもらっています。松山さんをポスドクから助教へ採用しました。原研病理で十数年来、放射線防護剤の研究に着実に取り組んできました。放射線誘発甲状腺発がんの年齢影響が新しい研究課題です。グローバルCOEのポスドクとして、被爆者腫瘍組織バンクの仕事を担当してもらっていた蔵重さんは原研分子の助教に異動となりました。甲状腺がん幹細胞をテーマに、新しい環境で生き生きと研究に取り組んでいます。今後も我々との共同研究は継続していきます。松山さんと蔵重さんの二人のポスドクが、COEプロジェクト終了後も、無事職場を確保できたのは何よりで、今後のさらなる活躍が期待されます。大学院生では、カザフスタンからの留学生ムサジャノワ ジャンナが昨年無事出産し、現在産休中、学位論文を同時に作成しています。10月から、腫瘍外科より社会人大学院生の大坪先生が仲間に加わってくれました。元助教の平川先生の仕事を後継し、乳癌のセンチネルリンパ節転移の診断法の開発に取り組んでいます。ほとんど基礎データはそろっていて、驚く程、高感度・高特異度・迅速・簡便です。キット化を模索中です。本年からは、さらに、甲状腺濾胞癌の新しい診断法についての研究に取り組んでもらっています。
原研創設から2年後の昭和39年(1964年)に、原研病理は「病態生理学部門」として誕生しました。従って、平成26年度に原研病理開講50周年を迎えます。教室は西森一正先生から関根一郎先生、そして現在にいたるまで、原研の病理学講座として継承されてまいりました。平成23年度は病理学会の100周年で、来年は日本病理学の偉人、吉田富三が、長崎医科大学で「長崎系腹水肉腫/吉田肉腫」を発見してから70周年です。当時、「吉田肉腫」は化学療法の有効性評価などの研究に広く用いられ、多数の研究業績につながりました。その中で、腫瘍細胞の移植が1個の細胞で十分であることが明らかにされています。この結果はまさに、現在のトピックスである「がん幹細胞」の存在を予言するものであり、特筆すべき業績です。吉田富三は「顕微鏡を考える道具とした最初の思想家」と称されます。「顕微鏡を考える道具」とする病理学の手法は、100年前も現在もかわっていません。私の研究室の壁に、中国出身で教室の同門である温先生からの贈り物の書を掛けています。温先生の友人である、清の第6代皇帝乾隆帝の第7代子孫、愛新覚羅恒紹 氏によるものです。「静観」には、心静かに事物の奥に隠された本質的なものを見極めること、という意味が込められていて、病理学の方法論に通じていると私は思います。病理学の果たすべき役割と可能性は、「基礎」から「臨床」まで広範におよぶことは言うまでもありません。我々の教室では、腫瘍・診断病理と放射線病理をキーワードに、静観と温故創新の精神で、研究、教育、地域医療貢献に微力を尽くしていく所存です。
腫瘍・診断病理学研究分野(原研病理)
教授 中島 正洋
原研創設50周年を迎えるにあたり
2010年3月、この原研病理の主任を拝命して、12年が経ちました。教室ホームページの「教授あいさつ」を最後に更新したのは7年前の平成27年3月です。教授としての折り返し地点は既に過ぎ、この機会にこれまでの12年を振り返り、残りの任期に当たりたいと考えます。
研究について:論文や学会発表の業績はこのHP中に掲載している通りです。この12年間で教室が主となり発表した論文は38編で、うち学位論文は9編含まれます。教室の研究テーマの柱は甲状腺を中心とする腫瘍病理学、原爆被爆者腫瘍・放射線関連発がん、新規分子病理診断指標研究で、この12年間変わっていません。現在進行中の研究課題は、1)甲状腺腫瘍内の組織構築の不均一性を分子病理学的に説明すること、2)「長崎被爆者腫瘍組織バンク」試料を用いた網羅的遺伝子解析による放射線誘発変異の特徴を発見できるか、またラット放射線誘発甲状腺癌モデルによる被ばくの分子指標を同定できるか、3)DNA損傷応答分子である53BP1は悪性腫瘍の普遍的な分子病理診断マーカーとなるか、というものです。これらの課題に関して学生や教員が学会発表し、病理学会学生発表賞、臨床内分泌病理学会研究賞、欧州病理学会の口演賞とポスター賞、国際臨床細胞学会のベストポスター賞、甲状腺学会研究賞と多数の表彰をいただいたのは今後の励みになりました。しかし、それぞれ難しいテーマであり、残念ながらまだまだゴールには程遠いと言わざるを得ません。今後も教室員と一緒に取り組み、甲状腺結節の病理診断への新提言、近距離被爆者腫瘍の遺伝子変異の網羅的解析、53BP1の病理診断への臨床応用の3つに挑戦していきたいと思います。
病理診断について:先代からの県内の病院の病理診断に加え、令和2年度より長崎大学病院地域病理診断支援センターが創設され、我々が担当することになりました。長崎県病院企業団からの委託で、現在令和4年度は助教、助手、医員3つのポストを得て、五島中央病院、上五島病院、対馬病院の病理診断と大学病院の病理診断の一部を担当しています。さらに令和元年からは甲状腺専門病院の病理診断を担当しています。多数の甲状腺・副甲状腺病変の病理を経験する機会に恵まれた幸運に感謝します。甲状腺腫瘍病理の共同研究もさせていただいていて、教室にとっては財産です。教室の病理専門医の養成に必要な十分な病理診断体制(剖検数を含め)は数的にも質的にも整っています。実際、12年間で教室から3名の病理専門医が生まれ、現在2名が長崎大学病理専門医プログラムでの修練中です。令和2年11月現在、我が国の病理専門医数は2620名、長崎県は27名です。これは人口10万人あたり2.0名に相当し、全国平均2.1名と同等ですが、10名(37%)が65歳以上と高齢化が顕著です。我が国の病理診断件数は2005年の2,143,452件から2018年は4,614,585と約2.2倍に増加、術中迅速件数は同57,684件から228,754件(約4.0倍)、がんの治療を決定する免疫染色件数は同151,248件から426,276件(3.8倍)と急増しています(厚生労働省 大臣官房統計情報部調査)。これらの数字を見ても病理専門医の現状は不足していることが明らかです。患者さんへの正確な病理診断提供のため、初期研修から県内の病院と大学との連携で専門医を育成する体制が必要と考えます。研修指定病院の長崎医療センターや嬉野医療センター、諫早総合病院の病理診断科には、原研病理同門の病理医が常勤していて、その連携で長崎県内の病理医を増やして参ります。
まとめ:この12年間で大学の運営体制、財政状況はドラスティックに変化しました。研究費獲得には常に競争力が問われるし、研究組織や教育プログラムはbuilt and scrapで新規性や革新性を持った改編が求められます。我々の所属する原爆後障害医療研究所は9年前(2013年)に大学附置研究所に改組され、6年前にはネットワーク型共同利用・共同研究拠点に認定されました。大学院専攻としては金沢・千葉大学との3大学共同の博士課程と福島医大との2大学共同の修士課程が新設され、原研の教室には多数の学生が所属して学んでいます。新型コロナのパンデミックやロシアのウクライナ侵攻といった社会不安は突発的に発生し、教育や研究活動に大きな変化を強いてきます。我々の課程の学生には旧ソ連邦圏の留学生が多く、将来に不安を抱えながら学業の継続を望む学生が少なくありません。変化のスピードの著しい大学の研究・教育環境や社会情勢からの影響に対応しながら、教室主任としての任にあたるには、教室員というマンパワーの活用と教員の目的意識の新陳代謝を促していくことが必要と考えます。教授就任時には二人病理医の困難な時期もありましたが、現在まで多くの同門の先生、共同研究者、教室員、大学院生に支えられて、これまで業務をこなしてきました。私の教室主任としての職務は、若い人材が集まり、ともに学び成長し、活躍・貢献できる場を与えることです。それには教室員全員に目的を共有してもらう事と若い人材を育てようとする想い・愛情が必要です。残された任期で、教室員と共により良い教室を作っていきたいと思います。
放射線医療科学専攻 放射線障害解析部門
腫瘍・診断病理学研究分野(原研病理)
教授 中島 正洋
教授就任のあいさつ
1.はじめに
この度、平成22年3月1日付けをもちまして、腫瘍・診断病理学研究分野(原研病理)を担当させていただくことになりました。初代の西森一正教授、先代の関根一郎教授に続いて、三代目となります。
私は佐賀県武雄市出身で、平成4年医学部卒業と同時に原研病理の大学院生となり人体病理学を学びました。平成8年からはUCLA School of Medicine, Cedars-Sinai Research Instituteにポスドクとして留学する機会を得ました。内分泌学の大家でありますShlomo Melmed教授の元で二年間、ラボでクローニングされた下垂体腺腫腫瘍遺伝子の発現・機能解析に従事しました。私にとって基礎実験のみに集中できたこの2年間はとても貴重であり、その後の研究に取り組む上でなくてはならない経験をさせていただきました。帰国後は、原研病理と同じく関根教授が主任でありました原研の資料収集保存部生体材料保存室(原研試料室)に配属され助手、講師、准教授を経て、現在に至っています。
2.研究について
私は人体病理学を専門分野とし、これまでに病理診断学、甲状腺腫瘍病理、被爆者腫瘍病理と分子病理学を領域とした研究に取り組んで参りました。原研試料室では、まず被爆者固形がんの病理診断データベース(DB)を作製しました。これには長崎被爆者11,802 人分の悪性腫瘍の病理診断が含まれていて、包括的に被爆者の保存試料の所在を知る事ができ、研究への活用が可能となりました。その結果、私どもからも被爆者腫瘍の保存パラフィン組織を材料とした分子病理学的研究成果が、徐々に国際学術誌に掲載されるようになりました。「被爆者の発がんリスクが現在でも続いている」という疫学情報は被爆者研究の共通認識となっています。自前の被爆者固形がんDBを検索しても、近距離被爆者に多重がん罹患率が高くなり現在も増加傾向にあることが判明しました。被爆者発がんへの放射線晩発影響の分子機構は未だ不明です。そのリスク亢進メカニズムの解明は、現在の原爆後障害研究における最重要課題であると同時に、一般の発がんリスクにつながるものと考えます。今後も、放射線被曝の影響を残す被爆者組織生体試料を活用した、晩発健康影響研究に取り組んでまいります。長崎大学グローバルCOEプログラム「放射線健康リスク制御国際戦略拠点」のプロジェクトの1つとして、平成20年から長崎大学病院と原爆病院外科の協力体制を得て、被爆者固形がんの新鮮凍結試料の収集が進行中です。将来的には、保存パラフィン切片ではできなかった網羅的な分子異常解析を新展開したいと思います。
原研病理は原爆後障害医療研究施設(原研)に属する病理学講座であり、高齢化していく原爆被爆者医療に貢献する腫瘍病理診断学と放射線晩発障害としての固形癌リスク解析に寄与する研究が望まれると理解します。発がんリスクが潜在する被爆者腫瘍組織は、がん研究の生体試料としても貴重であり、そこから得られる医学的情報を普遍化して社会へ還元することは、原研で研究をする我々の責務であると心得ます。最近、正常細胞では、放射線照射など、DNA障害性のストレスが加わった時に、DNA損傷が多数観察されてきますが、がん細胞では無処置で自然発生性にDNA損傷が亢進していることが判りました。1つの例を示します。子宮頸部腫瘍では多段階発がんが明らかです。DNA損傷応答の分子マーカーの発現を子宮頸部腫瘍で解析しますと、異形成の程度の亢進・がん化に伴い、この分子マーカーの発現が亢進していることが判りました。現在までに、高度異形成と上皮内がんの鑑別に、増殖細胞に発現する分子マーカーのサイズと数が有意な情報になることが判明しました。上皮内がんと診断されれば切除ですが、高度異形成であれば経過観察となることがある、治療方針の異なるこれら二つの病変の鑑別に有効と考えます。個々の細胞のDNA損傷応答の状態を解析することで、腫瘍の発生段階を知ろうとする試みは、独創的発想であり、すでに甲状腺がんと皮膚がんにおいて論文発表しています。自然発生性DNA損傷応答の亢進はゲノム不安定性を示唆する現象であり、ゲノム不安定性が腫瘍のもつ普遍的細胞特性であることを考慮しますと、普遍的腫瘍マーカーとして、腫瘍の診断・治療に貢献できる分子病理診断法への応用に期待がもてます。
3.病理医の育成について
診断病理学にも積極的に取り組んでまいります。「がんの2015年問題」と表現されるように、我が国のがん患者数は2015年にほぼ倍増し、2050年まで横ばいで推移することが試算されていて、今後がん患者数とともに病理診断件数が増加することが予想されます。さらに、縮小根治術が一般的になってくることにより、術中迅速診断を含め病理学的評価項目は増加する一方です。すなわち、先進医療での病理学の役割は一層高まっているにもかかわらず、病理医の不足が危機的状況であることは一般には知られていません。2008年の日本医師会からの報告によりますと、診療科別にみた最低必要医師数倍率は、病理診断科で最も高く(3.77倍)、婦人科(2.91倍)や救急科(2.07倍)の現状より、必要医師数が不足しています。長崎県の専門病理医不足の現状も厳しく、少子高齢化が進んでいます。平成20年度には「病理診断科」が標榜化され病理医に個人開業という選択肢も増えました。病理医の育成には、学部教育からの病理学への興味・動機付けが第一に重要で、研修医には臨床科としての病理学の魅力を伝え、専門病理医を志す若手医師の育成に微力を尽くしていく所存です。
4.まとめとして
西洋医学発祥の地である長崎大学医学部では、開学の祖ポンペの時代(1859年)より、解剖学とともに病理総論の講義が始まっています。病理学は、当時最先端の学問であったわけですが、形態学を重視するHE染色による古典的病理学の専門性は今もなお高く、現代医学においてもそのニーズは益々高まっています。原研病理では、この古くて新しい病理学を学問的基盤とし、被爆者腫瘍研究、診断病理学と分子病理学を3つの柱と位置付け、研究と教育に取り組んでいく所存です。被爆者腫瘍研究では、放射線の外照射を受け発がんのリスクが長期潜在する、世界で唯一の生体試料である被爆者腫瘍組織バンクを活用し、晩発性発がんリスク亢進の分子メカニズムの解明を目指します。同時に人体病理学の高い専門的知識と能力を有す、病理専門医を育成し、地域医療に貢献できる人材を輩出したいと思います。分子病理学では被爆者腫瘍研究により得られた知見から、普遍的腫瘍組織マーカーに足るべき新規分子診断法を創出してまいります。放射線障害や被爆地という、特異性からの普遍的知見の創出を目標に、被爆者研究から得られる医学的情報を国際社会へ発信していきたいと考えます。
放射線医療科学専攻 放射線障害解析部門
腫瘍・診断病理学研究分野(原研病理)
教授 中島 正洋