| |
法的な意味での被爆者とは、原爆被災者で被爆者健康手帳を交付されている人です。被爆者は被災しただけでなく、放射線の被曝(ひばく)をしています。特に原爆放射線を受けて晩期に起こる障害は被曝から数十年たって発生するので、被爆者にとって心配の種になっています。晩期障害は被曝放射線量と関係があり、被曝線量が多くなるほど障害の発生する割合が高くなります。
原爆放射線は3つに分けられます。爆発中心から発生した一次放射線、爆発後に生じた放射能をもった灰などの放射性降下物(フォールアウト)から発する放射線、そして一次放射線が地表の土や石に吸収された放射能から発する残留放射能です。原爆放射線の大半は一次放射線であり、他の放射線は全体の10分の1以下です。
また、原爆放射線はガンマ線と中性子線の二種類の放射線が含まれています。原爆放射線の大半はガンマ線であり、中性子線は全体の約10分の1です。
放射線は測定器で測れます。しかし、原爆が投下されたときには、測定器が準備してあったわけではなく、一次放射線は爆発後、すぐ消えてしまうので、測定器で測ることはできません。
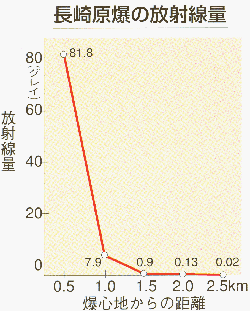 そこで、理論的な計算が3つのことを考えてなされました。最初に原子核分裂をしたウランやプルトニウムの量を考えに入れます。次に原爆の構造を考えます。最後に
爆発中心から放射線が地表に到達するまでの経路を考えます。爆心から遠く離れるほど被曝線量は減ります。(グラフ) そこで、理論的な計算が3つのことを考えてなされました。最初に原子核分裂をしたウランやプルトニウムの量を考えに入れます。次に原爆の構造を考えます。最後に
爆発中心から放射線が地表に到達するまでの経路を考えます。爆心から遠く離れるほど被曝線量は減ります。(グラフ)
原爆が落とされて約50年たった今でも、原爆放射線による変化は残っています。線量は被曝したれんがやかわらから分かります。れんがやかわらを暗室の中で数百度に熱すると、蛍光を発します。この蛍光量は被曝放射線量に比例するので、蛍光量を測れば被曝した放射線量を知ることができます。また、被曝した岩石からも分かります。岩石は微量の放射能を持っています。この放射能は一次放射線が吸収されてできたものです。
被爆者の体内にも残っています。一つは被爆者の歯です。被曝した歯を二つの強い磁石の間に置くと、弱い電気信号が出ます。電子スピン共鳴(ESR)信号です。信号の強さは被曝放射線量に比例します。被爆者の歯のESR信号を測れば分かります。
もう一つは血液細胞です。被爆者から採血し、リンパ球の染色体を調べます。ヒトはどの細胞も23組の染色体を持っていますが、被曝すると細胞の中の染色体が切れたり、切れた染色体が他の染色体とつながったりします。染色体異常です。リンパ球の染色体異常の数は被曝放射線量に比例するので、線量が分かるのです。
近距離被爆者のリンパ球に見られた染色体異常
2個の染色体が結合している。(矢印)
 |
被曝し、測定できる限られた数のれんがやかわらなどの試料を用いて、測定した被曝放射線量と計算した原爆放射線量は一致しました。したがって、この計算方法は正しいと言えます。この計算方法をDS86といいます。これは1986年に決められた原爆放射線量の推定方法という意味です。
では、どれだけの放射線を被曝したら人体に影響が出るのでしょう。現在の科学知識では0.2グレイ以上では何らかの影響が見られ、線量が増すとともに影響が現れる割合が増えます。0.2グレイ以下では影響は見られません。まず、被曝放射線を知ることが重要です。(グレイは吸収線量の単位で、1グレイは胃のレントゲン撮影約千回分に相当する) |
|