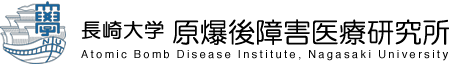川内村復興推進拠点

川内村は2011年3月の福島第一原子力発電所事故後、一時全村避難を余儀なくされましたが、事故収束後、2012年3月に福島県下で初めて「帰村宣言」を行い、他の自治体に先駆けて復興に取り組んでいます。
長崎大学は、2011年12月から川内村の復興に向けた取り組みを支援してきました。具体的には、帰村に先立って土壌中の放射性物質の測定を通じた住民の被ばく線量の推定を行い、帰村が科学的に見ても妥当であることを示したほか、2012年5月には保健学科修士課程の大学院生(保健師)が村に長期滞在し、放射線被ばくと健康に関する個別相談などを行うなど、帰村、復興に向けた村の取り組みを科学的な立場から支援してきました。
このような流れを受け、長崎大学と福島県川内村は2013年4月20日、川内村の復興と活性化に向けた包括連携に関する協定を締結し、村内に長崎大学のサテライト施設である「長崎大学・川内村復興推進拠点」を開設しました。拠点には現在、博士課程の大学院生でもある折田真紀子保健師が川内村に常駐し、村役場と密接に連携しながら、土壌や食品などの放射性物質測定を通じた住民の安全・安心の担保、測定したデータを基にしたきめの細かい健康相談の実施を行っています。また、保健学科の教員と連携しながら、震災後の長期避難による体力の低下などにも目を配り、地域リハビリなどの取り組みを通じた健康増進にも取り組んでいます。さらに、原子力安全研究協会の御協力のもと、ゲルマニウム半導体検出器を川内村に導入して、放射性物質の測定をより迅速かつ効率的に行う体制を整備しています。
このような拠点を活用した長崎大学と川内村の連携は、震災からの復興のモデルとして、注目を集めており、今後とも、原研を中心に長崎から福島への支援の柱として、活動を継続していく予定です。

富岡町復興推進拠点

富岡町は、平成23年3月11日の東日本大震災と、東京電力福島第一原子力発電所事故によって、地震、津波、原子力災害という3つの災害を同時に体験し、全町避難を余儀なくされました。
事故後、富岡町は除染をはじめとする復旧作業を着実に行い、原発事故から6年後の平成29年4月の帰還を開始しました。しかしながら事前の意向調査では、帰還を希望する住民は住民13,900人あまりのうち13.9%、特に10~20代では5.4%と、若い世代で帰還の意向を示す住民の割合が低くなっています。これは種々の社会的背景に加えて、放射線被ばくに対する不安も多分に影響していると考えられます。町は現在、本格復興のスタートをきるための基盤づくりを進めており、その中でも放射線量の検査などによる安全・安心の担保が重要な課題となっています。
長崎大学は平成25年4月に、富岡町に隣接する川内村と包括連携協定を締結し、村内に拠点(サテライトオフィス)を設置して保健師・看護師が常駐し、住民の外部被ばく線量や内部被ばく線量の測定・評価から、それらの測定結果をもとにした、個々人の状況に合わせたリスクコミュニケーション活動を行ってきました。その活動は、「住民、行政と専門家が一体となった原子力災害からの復興モデルケース」として、国内外から評価されています。さらに平成26年5月には福島未来創造支援研究センターを創設し、全学を挙げて福島復興と再生に様々な取り組みを実施しています。
国立大学法人長崎大学と富岡町との包括連携に関する協定締結式
今後、富岡町が住民の帰還を進めるなかで、長崎大学がこれまで川内村で培ってきた経験を活かし、専門的観点から富岡町の復興と活性化に資するため、富岡町と長崎大学が緊密な連携・協力を図ることを目的とする協定を締結し、富岡町健康福祉課内に長崎大学サテライトオフィスを設置しました。本協定では、(1)環境放射能評価や個人被ばく線量の測定を通じた、外部被ばく線量の評価に関すること、(2)食品等の放射性物質測定を通じた、内部被ばく線量の評価に関すること、(3)前二号を基にした健康相談や講演活動等を通じた住民の健康管理、安全・安心の担保に関すること、そして(4)その他本協定の目的を達成するために必要な事項、について長崎大学と富岡町が連係し協力することが記されていま